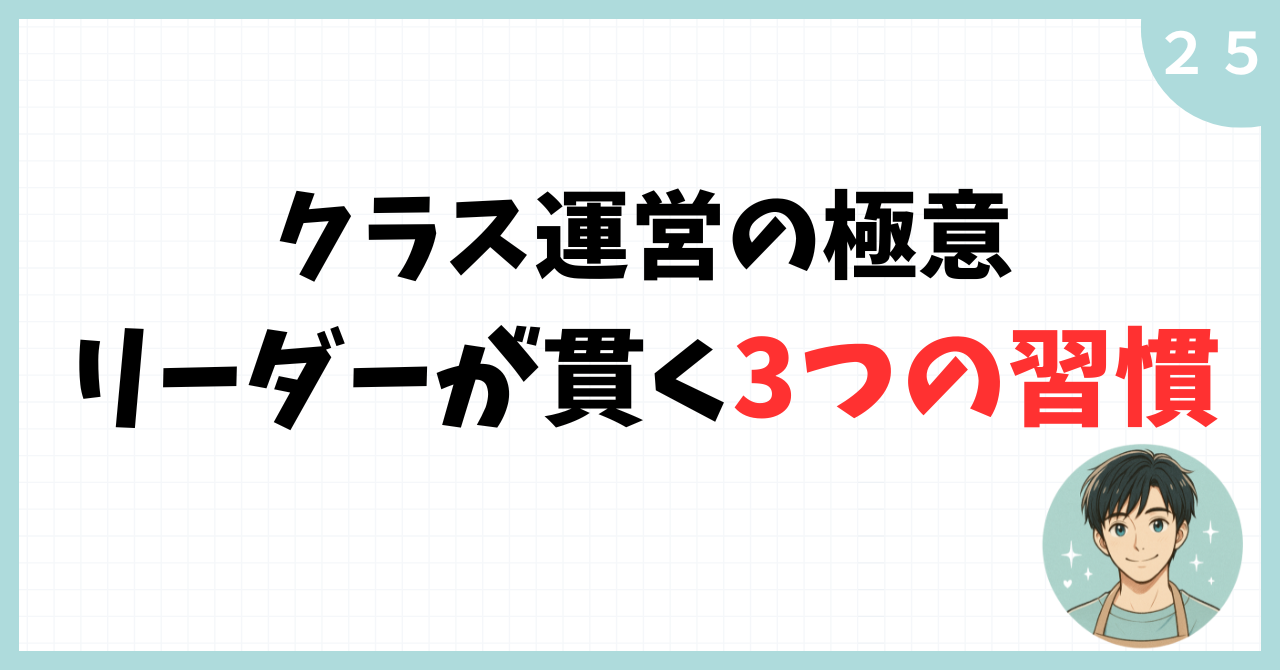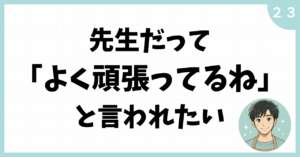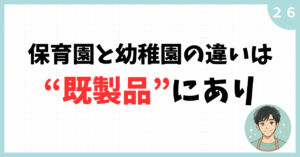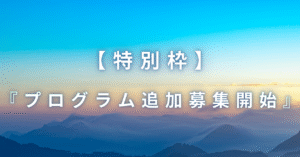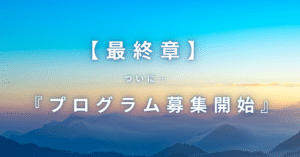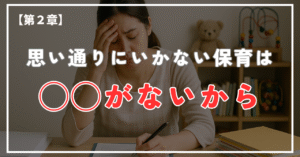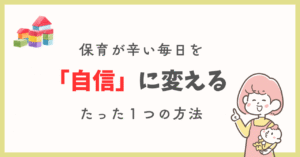リーダーが一番責任を負うから
クラス運営で
リーダーとサブの立場で
最も違うのは
「責任」です。
サブの立場なら
「最終判断は担任に
任せればいい」と
思えますが、
リーダーになると
そうはいきません。
子どもの安全、
保護者への対応、
行事の進行。
最後の責任を負うのは、
担任=リーダーです。
全体を見渡す意識を持つ
リーダーには、
全体を見渡す視点が
欠かせません。

- 子ども一人ひとりの姿を
見つつ、クラス全体の流れを
把握する - 保護者が安心できる
情報を届ける - 一緒に働く先生が動きやすい
環境をつくる
なぜなら、
も保育園全体も
**「組織で動くもの」**
だからです。
「自分が全部やらなきゃ」と
思うと必ず限界がきます。
周りに助けを求めながら、
組織の一員として
動く感覚を持つことで、
クラス運営は
大きく変わります。
その上で、私は次の3つの習慣
を実行しています。
どうやって:3つの習慣
① 保育者同士の連携を
細かくとる
自分が保育室を
離れるときは
必ず「○○で離れます」
と伝える。
「この子を見てほしい」
「ここをお願いします」と
具体的にお願いする。
先輩だからと遠慮せず、
自分から声を
かけることが大切。
なぜなら、
最終責任は自分に
返ってくるからです。
私は15分に1回ぐらい
コミュニケーションを
とっています。

② すぐに園長先生に
報告する
リーダーは責任を
持ちますが、
最終的な責任を取るのは
園長先生です。
園長先生が
「知らなかった」
となれば、
不信感につながり、
場合によっては
「園を辞めたい」
「転園したい」という
事態になることも
あります。
報告はしすぎるくらい
でちょうどいい
これを心に
留めておきましょう。
③ チェックリストを
フル活用する
名簿を使い、
「ケガ」
「保護者からの連絡」
「今日伝えること」を
細かく書き出す。
チェックリストは
漏れ防止だけでなく、
チーム全体の
安心材料になります。
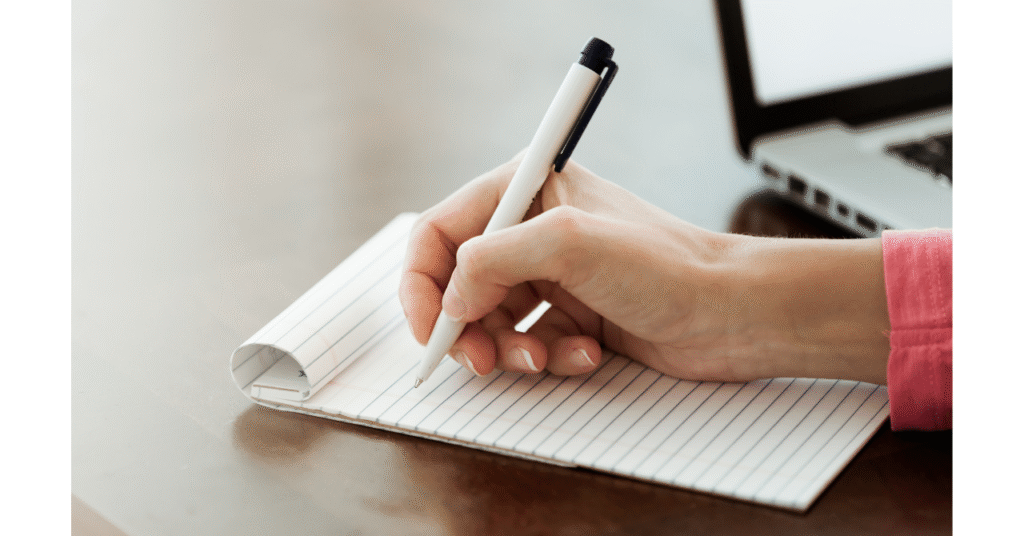
さらに、
ケガや対応だけでなく、
子どもの素敵だった瞬間
を書き残すと、
チームの雰囲気も
良くなります。
今すぐ:小さな一歩から
「見ていませんでした」では、
子どもの命を預かる
仕事では通用しません。
だからこそ、
保育者同士で連携を
取り合うことが大前提。
まずは明日、
「自分が離れるとき
に必ず伝える」
ことから始めて
みましょう。
「○○で抜けます」
「この子お願いします」
――その一言が、
クラスの安全と
信頼を守ります。
責任を背負うリーダー
だからこそ、
全体を見渡し、
組織で動く意識を持ち、
連携・即報告・仕組み化
を貫くこと。
この3つが、クラス運営を
安定させる最大のカギです。