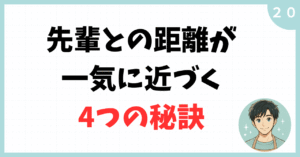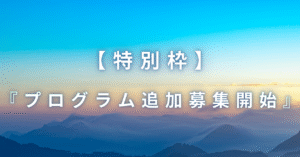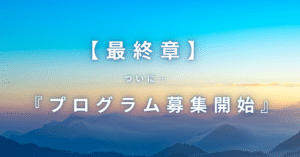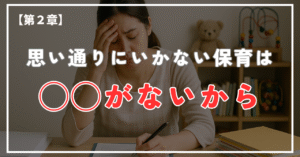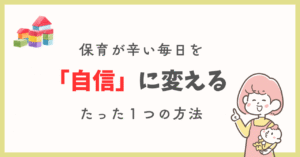保育士|行事って本当に必要?子どもに寄り添うあり方を考える
オーストラリアで
保育士として
働いている妹から、
ある日こんな話を
聞きました。
「行事?卒園式ぐらい
しかないで?」
「入園式すらない。
ましてや運動会なんて…」
その言葉に、
私は思わず耳を疑いました。
「えっ、日本で“当たり前”と
思っていた行事がないなんて!」
そこから改めて、
「行事って本当に子どもに
とって必要なのだろうか?」と
考えるきっかけに
なったのです。
若手の頃は“形にする”ことが精一杯
とはいえ、私自身も若手の頃は
とにかく“ついていくのに必死”。
まずは「形にすること」が
大切だと思い、
行事の準備や練習も
全力でこなしていました。
「先輩はどんな環境を
作っているんだろう?」
「どんな声かけを
しているんだろう?」
それをひたすら
吸収する毎日。
正直、そのときは余裕なんて
ありませんでした。
でも頭の片隅では、
「これって本当に必要なことなの?」
「子どもたちは目を
輝かせているかな?」と
問いかけながら関わろうとしていた
自分もいました。
その小さな疑問が、のちに
“行事を子どもの目線で見直す”
という考えに
つながったのだと思います。
行事よりも大切なのは“日常の積み重ね”
子どもにとって大切なのは、
行事の完成度ではなく
「日々の体験」です。
実際に年度末に
「この1年で楽しかったこと」を
子どもたちに尋ねると、
行事の話はほとんど出ません。
代わりに出てくるのは――
・夢中で虫取りをしたこと
・友達とごっこ遊びを楽しんだこと
・水遊びで思いきりはしゃいだこと
・けんかして仲直りしたこと
子どもが心から
楽しかったと語るのは、
“自分で選んで夢中
になった遊び”や
“友達や先生と過ごした
安心の時間”。
つまり、**子どもにとっての宝物は
「特別な行事」より
「日常の遊びや関わり」なのです。
行事を見直すための3つの視点
しかし!!
行事をすべてなくす
必要はありません。
大切なのは
「やるかどうか」ではなく
「どうやるか」 です。
子どもの育ちに
寄り添う行事にするために、
次の3つの視点を
持てると安心です。
- 子どもが主体的に楽しめる
内容になっているか
「保護者に見せるため」
ではなく、子どもの声や姿
から企画する。 - 準備や練習の過程も
学びになっているか
“披露のための完成形”ではなく、
友達と協力したり工夫したり
する過程を大切にする。 - 保育者が穏やかな気持ちで
関われているか
忙しさやプレッシャーで
ピリピリするよりも、
笑顔で余裕を持って接する。
保育者の姿勢そのものが、
子どもの安心につながります。
今すぐできること
まずは「形にする」
そこから
「子どもにとって意味が
あるかどうか」
考えてみましょう。
私もまずは形にすることで
精一杯でした!
だけど
『この行事ってやらせてない??』
少し頭の片隅で考えるだけで
思考が変わってきます。
行事に振り回されず、
子どもの声を中心に据えた
保育を意識する。
その積み重ねが、
子どもの育ちに本当に寄り添う時間
をつくっていくのだと思います。